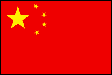 |
中国に旅行に行く前に。。。 |
| メニュー TOPページ 中国 中日通 人民日報 中国経済 地図 在上海日本総領事館 ビジネス 中国情報局 中国情報 中国とは 旅行に行く前に 中国について 中国って。。。 中国の人って 中国の地理 中国の地名 中国料理 中国関連news 台湾 韓国 インド シンガポール タイ インドネシア その他の国 リンク |
◎通貨(2002年4月) 中国の法定通貨は人民幣(レンミンピー:人民元:RMB)。であり、中国人民銀行が発行する。単位は「元」です。発音は“ユアン”です。紙幣には圓と印刷されています。補助単位は、角(ジャオ)と分(フェン)です。 紙幣は100元、50元、10元、5元、2元、1元、2000年10月からは20元の人民元紙幣が発行された。20元紙幣は赤茶色で、表に毛沢東の顔像、裏に桂林の景色が描かれている。 元の10分の1に当たる角、角の10分の1に当たる分の紙幣もそれぞれ3種類ある。また、1999年の建国50周年以降、毛沢東が印刷された新札が登場し、100元札は現在、2種類流通している。 硬貨は1元、5角、1角、5分、2分、1分の6種類だが、最近では、分は大型スーパーなどを除けばほとんど流通していない。 ◎紙幣(2002年4月) 1分、2分、5分、1角、2角、5角、1元、2元、5元、10元、20元、50元、100元 1999年の建国50周年以降、毛沢東が印刷された新札が登場し、100元札は現在、2種類流通している。 2000年10月からは20元の人民元紙幣が発行された。20元紙幣は赤茶色で、表に毛沢東の顔像、裏に桂林の景色が描かれている。 ◎硬貨:6種類(2002年4月) 1分、2分、5分、1角、5角、1元 最近では、分は大型スーパーなどを除けばほとんど流通していない。 1元(ユアン(Yuan)/通称:クアイ)=10角(ジヤオ/通称:マオ)=100分(フェン) 1角(ジヤオ/通称:マオ)=10分(フェン) ・レート 1人民元=14.9円(2001年12月) 1人民元=16.24円(2002年3月1日) ・両替(2002年4月) 両替は外国人観光客が宿泊する3つ星以上のホテル、空港内の両替所、友誼商店、銀行でできる。銀行の営業時間は、各銀行ごと、また規模によっても異なる。 両替が可能な主な銀行は中国銀行と交通銀行。中国銀行の場合は通常、月〜金曜日の9時〜16時30分、土曜日は午前中の営業になる(場所によって日曜の営業もある)。空港内の銀行は年中無休、深夜でも営業しているため、日本での両替は不要だ。トラベラーズチェックの両替は市中銀行で可能だが、ホテルでは宿泊客に限られる場合もある。 他の国とは異なり、レートはどこでも同じ。100元札がいちばん大きい通貨単位なので、高額の日本円を両替するとたちまち財布が膨れ上がることになる。 友誼商店や大型ショッピングセンター、高級ホテルなど外国人が多く集まる場所の周辺には、決まって闇の両替屋がたむろしている。レートはかなりよく、市民の間でも闇両替が一般化しつつあるようだ。ただし、公安による摘発も少なくなく、外国人旅行者にはおススメできない。 北京市海淀区にあるデパート・当代商城に100元札、50元札を10元札に両替する「自動換零機」(自動両替機)が登場した。 タクシーに乗るときや小さな商店で買い物をするときに必要なのが10元札。しかし、両替時には100元札や50元札の大きな額のお札が多くなってしまうなど、中国では細かいお金が極端に不足する場合が少なくない。買い物に訪れたついでに、両替しておくと便利だ。この機械にはニセ札を識別するための機能もあるので安心して利用できる。 空港ではタクシーなどお小遣い分の両替にとどめ、自分の宿泊するホテルで必要額を2−3日ごとに両替するのが賢明。両替時は原則としてパスポートを提示する。 中国元は6000元まで持ち出し可能だが、日本での両替はできない。出国時に元を日本円に再両替する際は、両替時に発行された外貨兌換証明書を提示しなくてはならないので、大切に保育しておくこと。 ◎時差(2002年4月) 日本との時差は1時間。日本よりも1時間、遅れている。(−1時間)国内においてはエリアによる時差やサマータイムはない。ただし、西部の新疆エリアにおいては、非公式の新疆時間(正式な時間=通称:北京時間)が存在する。 ◎ビザ(2003年9月) 中国に渡航する際には必ずビザを取得しなければならない。一般の観光の場合は「Lビザ」を取得する。これは1回の入国が可能な1次ビザと、3か月間に2回入国できる2次ビザ(いずれも滞在期間は、1回につき30日以内)の2種類がある。 ただし、2003年9月1日より、観光、商用、親族訪問又は通過の目的で中国へ入国する場合は、滞在日数が15日以内であれば、ビザなしで入国できることになりました。 ビザの申請には、残存有効期間が4か月以上あるパスポート、ビザ申請書、写真(4×3センチ)、中国での受け入れ先が発行する招聘状(インビテーション)が必要となるが、通常は旅行会社に手続きの代行を依頼するため、パスポートと写真を用意するだけでいい。 費用は旅行会社によって異なるが、一緒に航空券を購入し、10日ほどで1次ビザを取得する場合、申請料と手数料で最低6000〜7000円程度。ビザを特急(2〜3日)で取得する緊急申請はプラス5000円程度が相場だ。 Lビザは、現地の公安局で原則として1回に限り延長が可能。また、香港の外交部簽證弁事処では、日本に比べて手続きが簡単で、翌日にはビザが下りる。 中国への入国時には、入国カードと健康カードを提出する。いずれも、氏名、生年月日、国籍、パスポート&ビザ番号、滞在先などを記入しなければならないが、日本語(漢字)やローマ字で書いてもOK。また、滞在先が未定の人でも、北京なら「北京飯店」、上海なら「和平飯店」といった有名ホテルを記入しておけば問題ない。 ・ビザなし短期訪問について(2003年8月25日、中華人民共和国駐日本大使館HP) 1. 2003年9月1日より、普通パスポートを持つ商用、観光、親族訪問、トランジットの目的で入境する日本籍の者は、入境日から15日以内の場合ノービザ。その時、必ず外国人に開放する飛行場、港から入境し、イミグレーションで有効のパスポートを提出しなければならない。 2. 2003年9月1日より、普通パスポートを持ち、15日を越えて滞在する者、或いは留学、就業、定居、取材者、及び外交、公務パスポートの者は今まで通り、現在の法律と規定に基づいて、中国大使館総領事館でビザを申請する。 3. 日本の航空会社の乗務員は今までどおり中日間の協議に基づいて行われる。 4. 15日以内の滞在のつもりで入境した日本人がもし15日を越えるような場合は、現地の公安局の入境管理部門でビザの申請をする。停留期間を超過した者は、公安機関とイミグレーションで規定に基づく処罰が与えられることになるので注意。 ◎航空会社(2002年4月) 日本から中国に就航している航空会社は、日本航空(JL)、全日空 (NH)、日本エアシステム(JD)、中国国際航空(CA)、中国東方航空 (MU)、中国西北航空(WH)、中国西南航空(SZ)、中国南方航空(CZ)、 中国北方航空(CJ)、ユナイテッド航空(UA)、ノースウエスト航空 (NW)、パキスタン国際航空(PK)、イラン航空(IR)など。 成田、関西、名古屋、広島、福岡、長崎、沖縄(不定期)、岡山、新潟、富山、福 島、仙台、札幌のいずれかの空港と、北京、上海、ハルピン、瀋陽、大連、 青島、天津、西安、武漢、重慶、アモイ、広州、桂林、昆明の間を、直行便 と経由便が結んでいる。フライト時間(直行便)は、成田?北京約3時間 半、成田?上海3時間。 ◎電気事情(2002年4月) 50Hz、220V ◎クレジットカード(2002年4月) クレジットカードはVISA、マスター、JCB、アメリカンエキスプレス、ダイナースなどが高級ホテル、デパート、レストランなどで使用できる。ただし、地方によってはカードが使用できないところもあるので、現金の準備が必要となる。 中国の大都市では、ホテル、有名ショッピングセンターでクレジットカードが利用できる。 ◎チップ(2002年4月) 基本的には不要。ホテルで欧米人の宿泊客が自分たちの習慣にしたがって従業員に渡していることから、当然のように要求してくるものもいるが、高級ホテルでは、いかなる場合も受け取っては行けないと教育している所もあるくらい。無理に渡す必要はない。 ◎電話(2002年4月) 電話をかける場合、最も便利なのは宿泊先のホテル。たいていのホテルは、部屋から長距離通話、国際通話が可能。 日本に国際電話をかける場合は、外線発信番号を押した後、「00(国際電話識別番号)+81(日本の国番号)+0を除いた市外局番+番号」でOK。 国内の長距離通話は、日本の市外局番にある地方コード・局番がわからない場合、部屋に備えつけてあるコード一覧などで確認したうえでダイヤルする。コレクトコールは、ジャパンダイレクト(108-811)にかければ、日本人オペレーターが対応する。 一方、公衆電話はコイン式とカード式があるほか、カード式にもICカード式と磁気カード式の2種類があり、それぞれ電話機が異なる。外出先から長距離通話をかけるには、 1)長距離通話可のカードを使用して公衆電話を利用する 2)郵電局で申し込む 3)「長途」の看板のある有人式電話を利用する などの方法がある。 また、公衆電話で国際電話をかける場合は、外国人客が比較的多いホテルや友誼商店、高級デパートなどで国際通話が可能な電話機を捜す。 ◎郵便事情(2002年4月) 郵便局は中国語で、郵電局・郵局・郵政局という。ポストはグリーンでかなり目立つ。国土が広く、場所によって郵便事情は異なるが、北京や上海からなら航空便で1週間以内に到着する。ハガキ3.2元−、封書4.4元−。 中国から日本への郵便料金は、航空便でハガキ4.2元、封書が10グラムまで5.4元、20グラムまで6.4元。いずれも1週間−10日程度で日本へ届く。大至急という場合は「EMS(国際速達)」を利用する。北京・上海からであれば3−4日で日本へ届くうえ、書留なので安心できる。宛名も日本語で問題ない。2000年7月より料金が10%程度引き下げられ、ますます利用しやすくなった。 ◎インターネット事情(2002年4月) 中国でも、インターネット環境が急速に整備されつつあり、外国人客の多い大都市のホテルでは、通信用モジュラージャックが用意されているところもみられる。電圧は220ボルトなので、自分のPCのアダプターが対応していれば問題なく使える。 北京や上海には24時間営業のインターネットカフェも多い。しかし、ネットカフェのなかには、賭博ソフトやアダルトサイトなど法律で禁じられているサイトを提供しているところもある。そのため、中国政府はネットカフェに対して、ネット記録管理ソフトの使用や客の身分証明を義務付けている。 ◎車(2002年4月) 車は左ハンドル(右側通行)です。 ◎国際電話(2002年4月) 国番号:86 ◎祝祭日(2002年4月) 中国では、伝統にもとづく風情豊かな祝祭イベントが少なくない。日本と同じように、大都市では若者を中心として、伝統的な風習に対する関心は薄れがちではあるが、農村部や南方ではまだまだ古き良き伝統が受け継がれている。 なお、「正月」と言えば、西暦1月1日ではなく、旧暦1月1日を指すことからもわかるように、その多くは旧暦(農歴)で祝うため日程には注意したい。主な祝祭日は次のとおり。(旧)は、旧暦。 1月1日:元日。新年を祝う。国民の休日(休暇は1日)。 1月1日(旧):春節。 国民の休日(休暇は3日間)。大晦日(除夕)の晩は家族で餃子を食べ、1夜寝ずに新年を迎える(守歳)。ちなみに餃子は、中国語発音が昔の紙幣(角子)と同じで、形も昔の貨幣(元宝)と似ていることから、縁起のいい料理とされている。また、春聯(赤い紙にめでたい対句が書かれた一対の短冊)が玄関に貼り出されるほか、爆竹や打ち上げ花火といった春節ならではの風物詩も残っている。農村部では龍の舞い(龍燈舞=龍の形をした長い張り子の提灯を数人で高く持って街をねり歩く)も見られる。 1月15日(旧):元宵節。 提灯を飾り、家族団らんであん入り団子(元宵)を食べる。灯籠や吊り提灯になぞなぞを書きつけておき、それを解いた人が答えを紙に書いて貼りつけておく「灯謎」と呼ばれる遊びが行われる地方もある。 3月8日:三・八国際婦女節。女性のみ半日休み。 4月5日:清明節。 墓参りをして先祖の供養をする。江南地域では、清明団子(ハハコグサで作る)を食べる風習が残っている。 5月1日:五・一国際労働節。メーデー。国民の休日。 気候がよい時期に当たるため、都市近郊は小旅行の人々で賑わう。2001年の休日は、規定通りの3日間(5月1、2、3日)以外に、4月28日(土)・29日(日)の休みを5月4日(金)・7日(月)と入れ替えて、5月1〜7日まで7日間の大型連休となる。4月28日(土)・29日(日)は出勤日。 5月4日:五・四中国青年節。中学生以上は半日休み。 5月5日(旧):端午節。 古代の愛国詩人・屈原をしのぶ日と言われる。農村部では、五色の糸で作ったおもちゃを子供の体につけて厄除けをする俗習が残っているが、都市部ではチマキを食べるぐらい。 6月1日:児童節。いわゆる子供の日。小学生は休み。 7月1日:中国共産党創立記念日。 1997年からは香港祖国回帰記念日が加わった。党関係者を中心に記念行事を行う。 7月7日(旧):乞功節。七夕祭り。 8月1日:八・一中国人民解放軍記念日。 建軍節とも。1927年の南昌蜂起を記念し、人民解放軍・軍事機関関係者のみ半日休み。 8月15日(旧):中秋節。 月見を楽しみ、一家団らんで食事をする。親しい人との間で月餅を贈り合ったりもする。 9月9日(旧):重陽節。 菊の花を観賞し、菊花酒などを飲む。高いところへ登ると厄除けになることから、登山の風習もある。小学校などではこの日に遠足へ行く。 10月1日:国慶節。 国をあげて、1949年10月1日の中華人民共和国成立を祝う。国民の休日。5周年ごとに大規模なパレードなどが行われる(次回は建国55周年に当たる2004年)。 2001年の休日は、規定通りの3日間(10月1・2・3日)以外に、9月29日(土)・30日(日)の休みを10月4日(木)・5日(金)と入れ替えて、10月1〜7日まで7日間の大型連休となる。9月29日(土)・30日(日)は出勤日。 ◎姓名(2005年11月) 日本と同じく、姓の後に名が来ます。女性は結婚しても姓を変えません。 ◎教育(2005年11月) 日本と同じく、6・3・3制です。 |